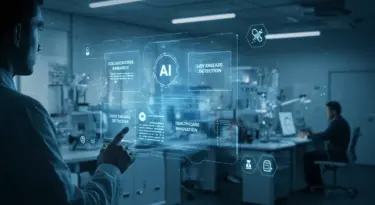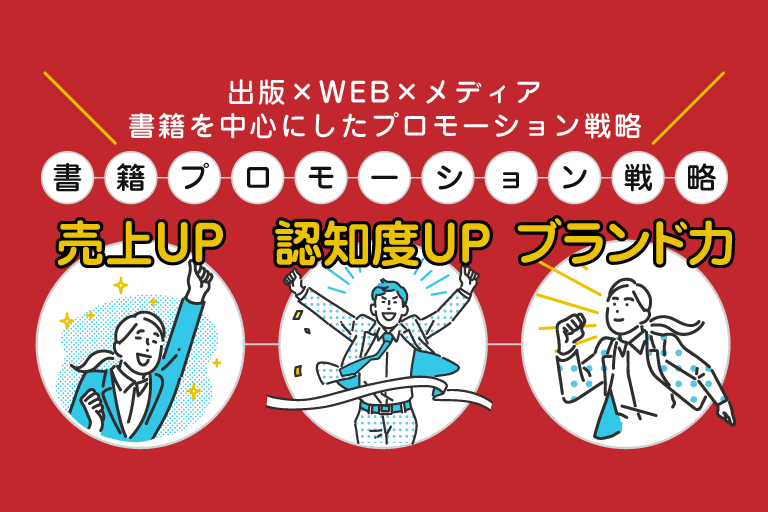この記事の要点
- プレスリリースのタイトルは、多忙な記者が「読む価値があるか」を3秒で判断する最重要要素であり、メディア掲載の成否を大きく左右します。
- 「結論ファースト」「具体的な数字」「30文字前後」など、ニュース価値を的確に伝えるための9つの基本原則を徹底することが不可欠です。
- 新商品発表、イベント告知、調査レポートなど、目的別に最適化されたタイトル例文を参考にすることで、より効果的なタイトルを作成できます。
- IT、製造、小売、医療など業界特有の文脈やキーワードを盛り込むことで、専門メディアの関心を引き、競合との差別化を図ることが可能です。
- AIツールはタイトル作成の効率を上げますが、最終的には人間の客観的な視点でのチェックと、メディアの読後感を想像した調整が成功の鍵となります。
なぜプレスリリースのタイトルは最重要なのか?メディア掲載を左右する3つの理由
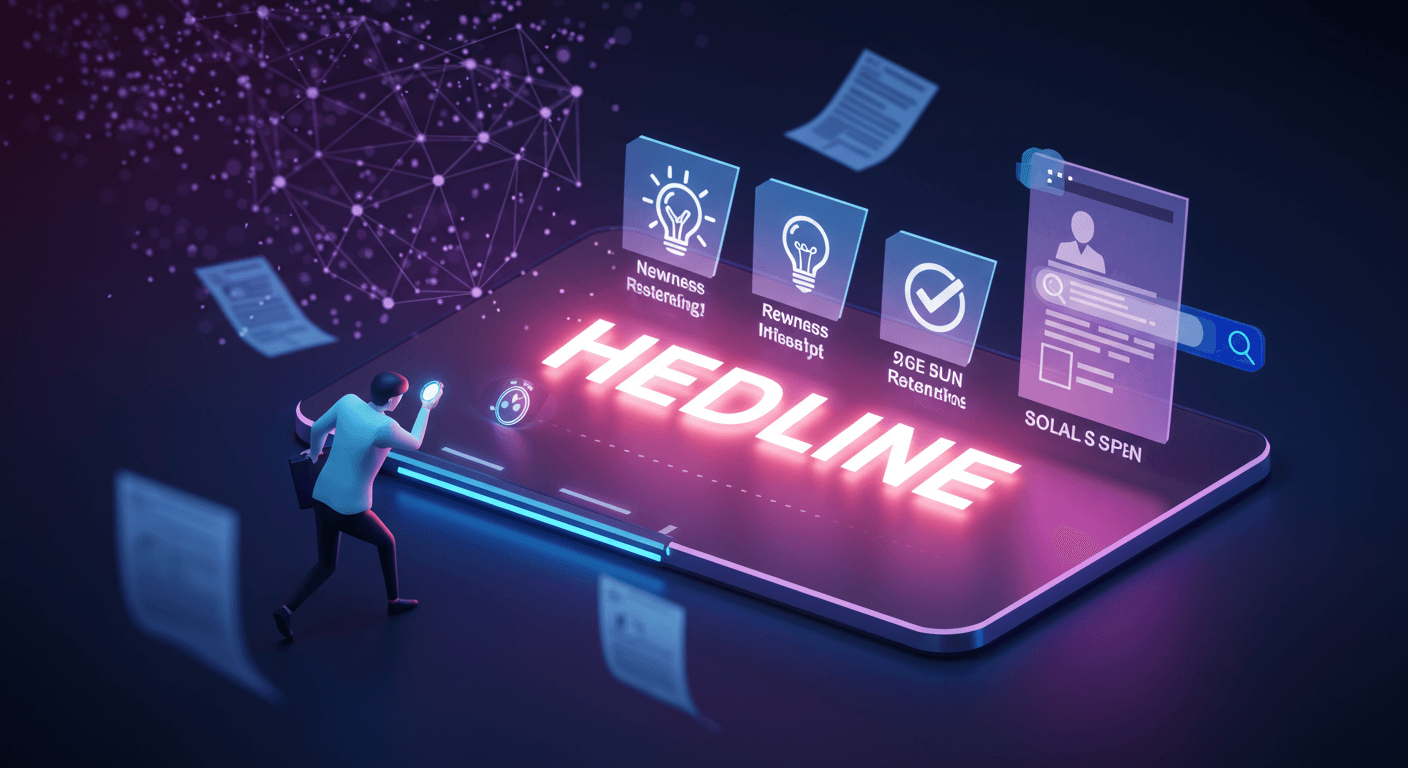
プレスリリースの成否は、タイトルで9割決まると言っても過言ではありません。毎日何百通ものリリースを受け取る多忙なメディア関係者にとって、タイトルは瞬時にニュースの価値を判断するための唯一の手がかりです。なぜ、これほどまでにタイトルが重要視されるのでしょうか。その理由は大きく3つあります。
1. 記者の「読む・読まない」を3秒で決定づけるから
記者は常に時間に追われています。受信トレイに届く大量のプレスリリースを一つひとつ熟読する時間はありません。彼らはまずタイトルに目を通し、「この記事は読む価値があるか」「自社の読者にとって有益な情報か」をわずか数秒で判断します。ここで興味を引けなければ、本文がどれだけ優れていても読まれることなく、ゴミ箱行きになってしまうのです。つまり、タイトルはメディア掲載への最初の、そして最も重要な関門と言えます。
2. ニュースの「価値」を端的に伝える役割があるから
優れたタイトルは、プレスリリースの内容、すなわち「ニュースバリュー」を凝縮して伝える役割を担います。何が新しいのか(新規性)、社会にどんな影響があるのか(社会性)、読者にどんなメリットがあるのか(有用性)といったニュースの核心を、タイトルだけで示唆できなければなりません。このニュースバリューが明確に伝わらないタイトルは、単なる企業広告と見なされ、メディアから敬遠されてしまいます。メディアが求めているのは広告ではなく、読者が知りたい「ニュース」なのです。
3. Webメディアでの「検索性(SEO)」にも影響するから
近年、プレスリリース配信サービスを通じてWebメディアに掲載されるケースが増えています。その際、タイトルは記事の見出しとしてそのまま使われることが多く、検索エンジンの評価(SEO)に直接影響します。ユーザーが検索しそうなキーワードがタイトルに含まれていれば、検索結果で上位に表示されやすくなり、より多くの人の目に触れる機会が増えます。メディアに取り上げられるだけでなく、その先の一般読者に情報を届けるためにも、タイトルの戦略的な設計は不可欠なのです。
メディアに取り上げられるプレスリリースタイトルの作り方【9つの基本原則】

メディア関係者の心を掴み、記事化へと繋げるためには、戦略的にタイトルを作成する必要があります。ここでは、広報のプロが実践する9つの基本原則を徹底解説します。これらの原則を理解し、組み合わせることで、あなたのプレスリリースがその他大勢に埋もれることなく、記者の目に留まる確率を劇的に高めることができるでしょう。初心者の方でもすぐに実践できる具体的なテクニックばかりですので、ぜひ一つひとつ確認しながら読み進めてください。
原則1:結論ファーストで「ニュースバリュー」を明確に
プレスリリースのタイトルで最も重要なのは、「何がニュースなのか」を最初に伝えることです。記者は結論を先に知りたいと考えています。回りくどい表現や前置きは不要です。「株式会社〇〇、△△を発表」のように、誰が何をしたのかを明確に示しましょう。
この「ニュースバリュー」には、新規性、社会性、意外性、時事性などが含まれます。例えば、「業界初」「日本初」といった新規性や、「〇〇問題の解決に貢献」といった社会性は、メディアが好む要素です。自社の発表が持つ最も強いニュース価値は何かを見極め、それをタイトルの冒頭に持ってくることが、記者の関心を引く第一歩となります。
「タイトルを見た瞬間に、記事の大枠が理解できなければ、そのリリースは読まない。我々には時間がないんだ。」
– 現役経済記者
この言葉が示すように、結論を後回しにする構成は致命的です。伝えたい情報の核心部分を、最も目立つタイトルの先頭で提示する。この「結論ファースト」の意識を常に持つことが、メディアに取り上げられるタイトル作成の基本中の基本です。
原則2:「5W1H」を意識して具体性を高める
ニュースの基本要素である「5W1H」(When:いつ, Where:どこで, Who:誰が, What:何を, Why:なぜ, How:どのように)をタイトルに盛り込むことで、情報の具体性が格段に向上します。もちろん、すべてを30文字程度のタイトルに詰め込むのは困難ですが、特に重要な「Who(誰が)」「What(何を)」は必須です。これに加えて、「When(いつ)」や「Why(なぜ)」などを補足することで、ニュースの全体像がより明確になります。
悪い例:「新サービス開始のお知らせ」
これでは誰が何を始めたのか全く分かりません。
良い例:「株式会社〇〇、テレワーク導入企業向け勤怠管理システム『△△』を4月1日より提供開始」
この例では、「Who(株式会社〇〇が)」「What(勤怠管理システム『△△』を)」「When(4月1日より)」「Why/Whom(テレワーク導入企業向けに)」といった要素が含まれており、記者はニュースの概要を瞬時に把握できます。どの要素を優先的に入れるべきか、リリースの内容に応じて判断しましょう。
原則3:最適な文字数は30文字前後
プレスリリースのタイトルは、長すぎても短すぎてもいけません。一般的に、最適な文字数は30文字前後とされています。これには明確な理由があります。
まず、多くのプレスリリース配信サービスやメーラーでは、件名が表示される文字数に限りがあります。30文字を超えると、タイトルが途中で切れてしまい、最も伝えたい部分が記者の目に触れない可能性があります。また、Yahoo!ニュースなどの主要なニュースサイトで表示される見出しも、おおむね30文字以内に収められています。これは、人間が瞬時に内容を理解できる文字数の限界とも言われています。
逆に短すぎると、必要な情報が不足し、ニュースの価値が伝わりません。「新製品発売」だけでは、何のこっちゃ分かりません。必要な情報を盛り込みつつ、いかに簡潔にまとめるか。このバランス感覚が、タイトル作成の腕の見せ所です。まずは30文字を目安に作成し、そこから不要な言葉を削ぎ落としていく作業を心がけましょう。
原則4:具体的な「数字」を入れてインパクトを出す
タイトルに具体的な「数字」を入れると、客観性とインパクトが飛躍的に高まります。抽象的な表現よりも、数字で示す方が説得力が増し、記者の注意を引きやすくなるのです。これは「メディアフック」と呼ばれるテクニックの一つです。
例えば、以下の2つのタイトルを比べてみてください。
- 抽象的な例:「多くの企業が導入した新システム」
- 具体的な例:「導入企業500社突破!〇〇社の新システム、契約継続率98%を達成」
後者の方が、実績が明確でニュースとしての価値が高いことが一目瞭然です。価格(例:「月額500円から」)、実績(例:「売上300%増」)、期間(例:「開発期間3年」)、調査結果(例:「利用者の9割が満足と回答」)など、アピールできる数字は積極的に活用しましょう。数字は嘘をつきません。その客観性が、プレスリリースの信頼性を高め、メディアが取り上げる価値のある情報だと判断させる強力な武器になります。
原則5:固有名詞(企業名・サービス名)を活用する
タイトルには、自社の「企業名」や「サービス名・商品名」といった固有名詞を必ず入れましょう。これは当たり前のようで、意外と忘れがちなポイントです。
固有名詞を入れることには、2つの大きなメリットがあります。第一に、ニュースの主体が誰であるかを明確にし、情報の信頼性を高める効果があります。無名の企業からの情報よりも、企業名が明記されている方が、記者は安心して内容を確認できます。第二に、Webメディアに掲載された際のブランディング効果とSEO効果です。記事に企業名やサービス名が記載されることで、認知度が向上します。また、ユーザーがその固有名詞で検索した際に、記事がヒットしやすくなるというメリットもあります。
特に、提携や協業に関するリリースの場合は、相手先の企業名も入れることでニュースバリューが高まります。知名度の高い企業や団体と組む場合は、その名前を積極的に活用し、タイトルの権威性を高めましょう。例:「株式会社〇〇、大手商社△△と資本業務提携」
原則6:専門用語や形容詞、誇張表現は避ける
プレスリリースは、企業の公式発表文書です。そのため、客観性と正確性が何よりも求められます。読者である記者や、その先の一般消費者が誤解するような表現は厳禁です。
特に注意したいのが以下の3つです。
- 専門用語・業界用語:自社内では当たり前に使っている言葉でも、社外の人間には通じないことが多々あります。例えばIT業界の専門用語をそのまま使っても、経済部の記者には理解できません。「誰が読んでも分かる平易な言葉」を心がけましょう。
- 曖昧な形容詞:「画期的な」「素晴らしい」「最高の」といった主観的な形容詞は避けましょう。何が画期的なのかを、具体的な事実や数字で示すことが重要です。
- 誇張表現:「世界初」「業界No.1」といった表現を使う場合は、その根拠を必ず明記する必要があります。客観的な調査データなど、信頼できるエビデンスがない限り、安易に使うべきではありません。景品表示法に抵触するリスクもあります。
信頼を損なう表現は、メディアからの評価を著しく下げてしまいます。常に客観的な事実に基づいた、誠実な言葉選びを徹底してください。
原則7:サブタイトルを効果的に活用する
メインタイトルだけでは伝えきれない情報を補足したい場合、サブタイトルが非常に有効です。メインタイトルで最も重要なニュースの核心(結論)を伝え、サブタイトルでその背景や詳細、社会的意義などを補足する、という役割分担が理想的です。
例えば、以下のような構成が考えられます。
メインタイトル:
株式会社〇〇、AIを活用した自動翻訳システム「△△」を提供開始
サブタイトル:
〜専門分野の翻訳精度95%を実現し、企業の海外進出を支援〜
このように、メインタイトルで「Who」と「What」を明確に伝え、サブタイトルで「How(どのように優れているか)」や「Why(なぜ重要なのか)」を補足することで、ニュースの全体像がより深く伝わります。メインタイトルは30文字前後で簡潔に、サブタイトルで少し説明を加える、というバランスを意識すると良いでしょう。プレスリリース配信サービスの多くは、メインタイトルとサブタイトルの入力欄が分かれているため、この機能を最大限に活用しましょう。
原則8:読み手のベネフィットや社会性を盛り込む
メディアがニュースを取り上げるかどうかを判断する際、その情報が「読者(視聴者)にとってどのような価値があるか」という視点を非常に重視します。そのため、タイトルに読み手が享受できるメリット(ベネフィット)や、そのニュースが持つ社会的な意義を盛り込むことは、極めて効果的なアプローチです。
例えば、単に「新機能をリリース」と伝えるのではなく、「〇〇機能の追加で、作業時間が平均30%削減」と表現すれば、ユーザーにとっての直接的なベネフィットが明確になります。また、「フードロス削減に貢献する新サービス」や「地域の活性化を目指すイベント開催」のように、社会的な課題解決に繋がるテーマは、メディアの関心を引きやすい傾向にあります。自社の発表が、個人の生活や社会全体に対して、どのようなポジティブな影響を与えるのか。その視点からタイトルを考えることで、ニュースの価値を一層高めることができます。
原則9:客観的な視点で複数案を検討する
最高のタイトルは、一度で生まれるとは限りません。担当者一人の視点では、どうしても思い込みや主観が入りがちです。そこで重要になるのが、客観的な視点を取り入れるプロセスです。
まずは、これまで紹介した8つの原則を踏まえ、最低でも5〜10個のタイトル案を考え出してみましょう。切り口を変え、様々なキーワードを組み合わせて、バリエーションを広げます。次に、その複数案を、社内の別部署のメンバーや、可能であれば社外の知人など、そのニュースに詳しくない第三者に見てもらいましょう。「どのタイトルが一番興味を引かれるか」「意味が分かりやすいか」といったフィードバックをもらうことで、自分では気づかなかった問題点や、より魅力的な表現のヒントが見つかります。
「自分たちが『すごい』と思っていることと、世間が『ニュースだ』と感じることは違う。そのズレを修正するのが広報の仕事。だからこそ、第三者の冷静な目は不可欠です。」
– ベテラン広報コンサルタント
このプロセスを経ることで、独りよがりなタイトルを避け、より多くの人に響く、洗練されたタイトルへと昇華させることができるのです。
【目的別】すぐに使える!プレスリリースタイトル例文15選

ここでは、プレスリリースの目的別に、すぐに使えるタイトルの型と具体的な例文を紹介します。自社の状況に合わせて単語を入れ替えるだけで、効果的なタイトルを作成できます。これらの例文を参考に、メディアの目に留まる魅力的なタイトル作りに挑戦してみてください。
新商品・新サービス発表のタイトル例
新商品や新サービスの発表は、プレスリリースの王道です。ニュースバリューを明確にするため、「新規性」「ターゲット」「解決する課題」を盛り込むのがポイントです。
- 【型】[企業名]、[ターゲット層]向け[商品カテゴリ]「[商品名]」を[発売日]に発売
例文:株式会社ABC、テレワーク中の運動不足に悩むビジネスパーソン向け家庭用フィットネスバイク「CycleFit」を5月1日より販売開始 - 【型】[業界初/日本初]の[特徴]を実現した[サービス名]、[提供開始日]より提供開始
例文:業界初、AIによる自動献立提案機能を搭載した食品宅配サービス「Smart Kitchen」、本日よりβ版の提供を開始 - 【型】[既存商品の課題]を解決する[新商品名]が登場。〜[具体的なベネフィット]〜
例文:従来の課題だったバッテリー持続時間を3倍に延長した新型ドローン「AirWing Pro」が登場。〜8時間の連続飛行で広範囲の測量が可能に〜
イベント・セミナー開催のタイトル例
イベントやセミナーの告知では、「誰が」「何をテーマに」「いつ・どこで」開催するのかを明確に伝える必要があります。著名な登壇者や参加するメリットをアピールすると効果的です。
- 【型】[企業名]、[イベントテーマ]に関するオンラインセミナーを[開催日]に無料開催
例文:株式会社DEF、中小企業のDX化を支援する「クラウド会計導入実践セミナー」を6月15日に無料オンライン開催 - 【型】[著名な登壇者]氏が登壇![イベント名]を[開催場所]で[開催日]に開催
例文:経済評論家〇〇氏が特別講演!次世代マーケティングカンファレンス「Marketing Vision 2024」を東京ビッグサイトで7月10日に開催 - 【型】[参加対象]必見![イベントのベネフィット]が学べる[セミナー名]開催
例文:スタートアップ経営者必見!3ヶ月で売上を200%にしたグロースハック術が学べる限定セミナー、参加者募集開始
調査結果・レポート発表のタイトル例
独自の調査結果は、客観的なデータとしてメディアに引用されやすい非常に価値の高いコンテンツです。「調査対象」「調査テーマ」「最も興味深い発見」をタイトルで示しましょう。
- 【型】[調査テーマ]に関する意識調査、[最も意外な結果]が明らかに
例文:Z世代の消費行動に関する意識調査、7割以上が「企業の環境への取り組み」を商品購入時に重視していることが判明 - 【型】[企業名]、[調査レポート名]を発表。〜[調査から見えた傾向]〜
例文:株式会社GHI総合研究所、「2024年上半期 全国主要都市のオフィス市場動向レポート」を発表。〜都心回帰の動きが鮮明に〜 - 【型】[調査対象]の[割合]が[特定の行動・意見]と回答。[調査名]より
例文:小学生の保護者の8割が「プログラミング教育に不安を感じている」と回答。株式会社GHI実施「子どもの習い事に関する調査」より
業務提携・資金調達のタイトル例
提携や資金調達のニュースは、企業の成長性や将来性を示す重要な指標です。提携先の企業名や調達額、そして「目的」を明確にすることがニュース価値を高めます。
- 【型】[自社名]、[相手企業名]と[提携内容]で業務提携
例文:AI開発の株式会社JKL、医療データ解析の株式会社MNOと次世代診断支援システムの共同開発で業務提携 - 【型】[自社名]、シリーズ[ラウンド]で[調達額]の資金調達を実施。〜[目的]を加速〜
例文:SaaSスタートアップの株式会社PQR、シリーズAで総額5億円の資金調達を実施。〜プロダクト開発体制の強化と海外展開を加速〜 - 【型】[自社名]、[引受先]を引受先とする第三者割当増資を実施
例文:株式会社STU、大手ベンチャーキャピタルVWXを引受先とする第三者割当増資により、事業基盤の強化へ
CSR活動・社会貢献のタイトル例
企業の社会貢献活動は、社会性の高いニュースとしてメディアの関心を集めやすいテーマです。活動の具体的内容と、それによってもたらされる社会的なインパクトを伝えましょう。
- 【型】[企業名]、[社会課題]の解決を目指し、[具体的な活動内容]を開始
例文:株式会社いろは、地域のフードロス削減を目指し、規格外野菜を活用した子ども食堂への食材提供を本日より開始 - 【型】[活動内容]により、[具体的な成果]を達成
例文:全社の照明をLEDに切り替え、年間CO2排出量50トンの削減を達成。〜サステナビリティ経営の取り組みを強化〜 - 【型】[企業名]、[支援先]へ[支援内容]を実施
例文:株式会社XYZ、令和6年能登半島地震の被災地支援として、売上の一部である1,000万円を日本赤十字社へ寄付
【競合と差をつける】業界別タイトル作成のポイントと事例
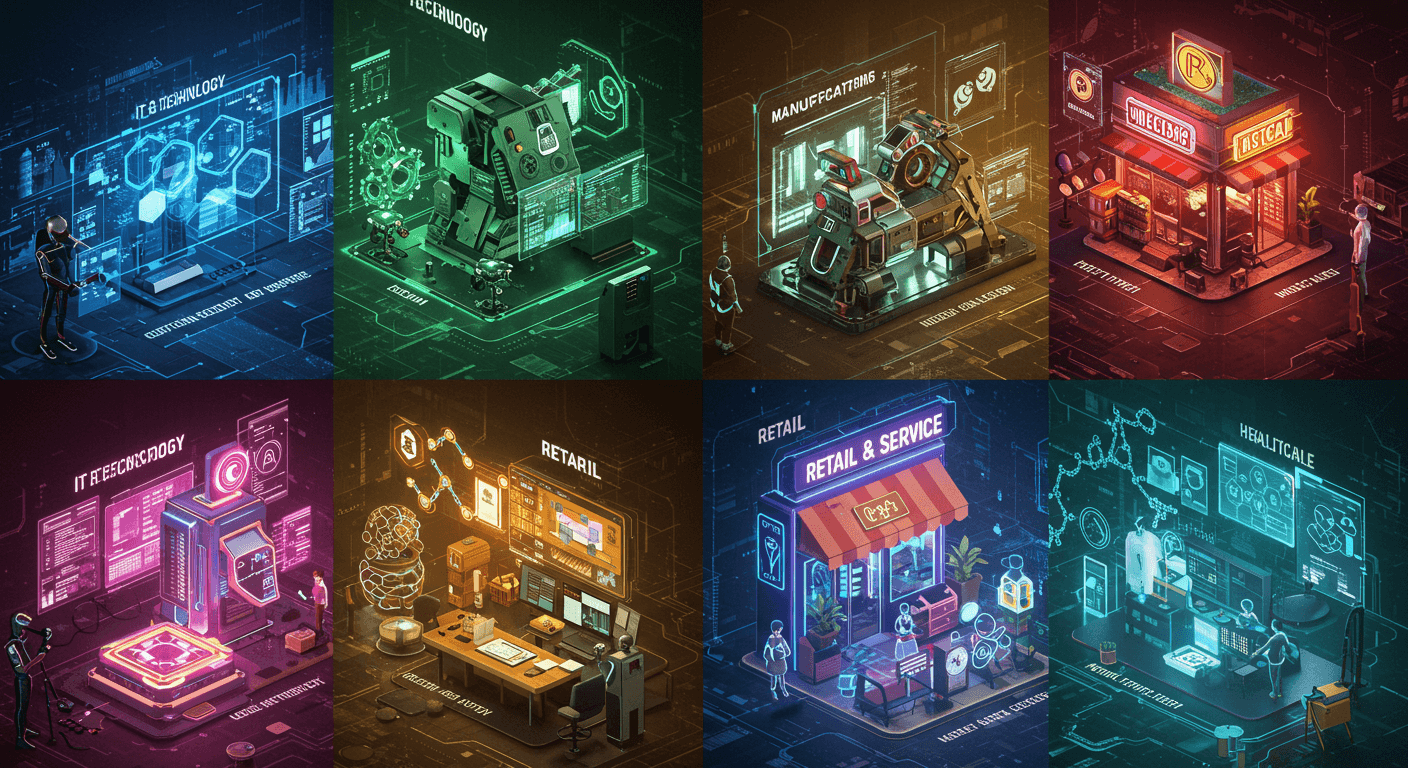
プレスリリースのタイトルは、業界の特性や、その業界を専門とするメディアの関心事を考慮することで、より響くものになります。ここでは主要な4つの業界を例に、競合と差をつけるためのタイトル作成のポイントと具体的な事例を紹介します。自社の業界に近いものを参考に、より専門性の高いタイトルを目指しましょう。
IT・テクノロジー業界向けのタイトル作成術
技術革新が速いIT業界では、「新規性」「独自性」「将来性」が重要なキーワードです。専門用語は避けつつも、技術的な優位性を分かりやすく伝える必要があります。また、具体的な導入効果やビジネスへのインパクトを示すと、経済メディアなどの関心も引きやすくなります。
ポイント:
- 「業界初」「独自技術」などの言葉で新規性をアピールする。
- AI、DX、SaaS、ブロックチェーンなど、時流に合ったキーワードを盛り込む。
- 「〇〇を自動化」「コストを〇%削減」など、導入後の具体的なベネフィットを数字で示す。
タイトル例:
- 株式会社TechForward、独自開発の自然言語処理AIを活用し、議事録作成を90%自動化するSaaS「Minutes AI」を提供開始
- 製造業のDXを推進する株式会社FactoryTech、大手自動車メーカー〇〇と工場の予知保全システムに関する実証実験を開始
製造・メーカー業界向けのタイトル作成術
製造業では、「技術力」「品質」「歴史」や、環境配慮(サステナビリティ)への取り組みがニュース価値を持ちます。BtoB(企業向け)の製品であっても、その技術が最終的に消費者の生活をどう豊かにするのか、という視点を加えると、一般メディアにも取り上げられやすくなります。
ポイント:
- 「創業〇年」「伝統の技」などで歴史と信頼性をアピールする。
- 新素材、特許技術、環境配慮型製品など、技術的な強みを具体的に記述する。
- 「耐久性2倍」「軽量化30%成功」など、従来製品との比較を数字で示す。
タイトル例:
- 創業100年の〇〇金属、航空宇宙産業向けに従来比2倍の強度を持つ新合金「Titan-X」の開発に成功
- 株式会社EcoMaterial、植物由来原料100%の生分解性プラスチックを開発。〜海洋プラスチック問題の解決に貢献〜
小売・サービス業界向けのタイトル作成術
消費者向けのビジネスが中心の小売・サービス業界では、「トレンド」「顧客体験」「限定性」がフックになります。季節性のあるイベントや、新しいライフスタイルを提案するような切り口は、情報番組やライフスタイル誌などの関心を引きます。
ポイント:
- 「期間限定」「〇〇店限定」などで特別感を演出する。
- 「おうち時間」「ウェルネス」など、世の中のトレンドや消費者のインサイトを反映させる。
- 有名人や人気キャラクターとのコラボレーションをアピールする。
タイトル例:
- 百貨店〇〇、開店50周年を記念し、人気パティシエ△△氏とコラボした限定スイーツを7月1日より期間限定で販売
- ホテル△△、”何もしない贅沢”をコンセプトにしたデジタルデトックスプランを提供開始。〜コロナ禍で疲れた心身を癒す新しい旅の形を提案〜
医療・ヘルスケア業界向けのタイトル作成術
人々の健康や生命に直結する医療・ヘルスケア業界では、情報の「信頼性」「正確性」「社会性」が何よりも重要です。薬機法(旧薬事法)などの関連法規を遵守し、効果効能を断定するような表現は絶対に避けなければなりません。大学や研究機関との共同研究などは、信頼性を高める強力な要素となります。
ポイント:
- 大学や公的研究機関との共同研究・開発であることを明記する。
- 「〇〇病の早期発見に繋がる可能性」など、過度な期待を煽らない慎重な表現を心がける。
- 高齢化社会、予防医療といった社会的なテーマとの関連性を示す。
タイトル例:
- 〇〇大学医学部と共同研究、AI画像解析による特定疾患の早期発見支援システムの臨床研究を開始
- 株式会社HealthSupport、高齢者向け見守りサービス「あんしんセンサー」に転倒検知機能を追加。〜深刻な事故を未然に防ぎ、家族の安心に貢献〜
【最新トレンド】AIを活用したプレスリリースタイトル作成術
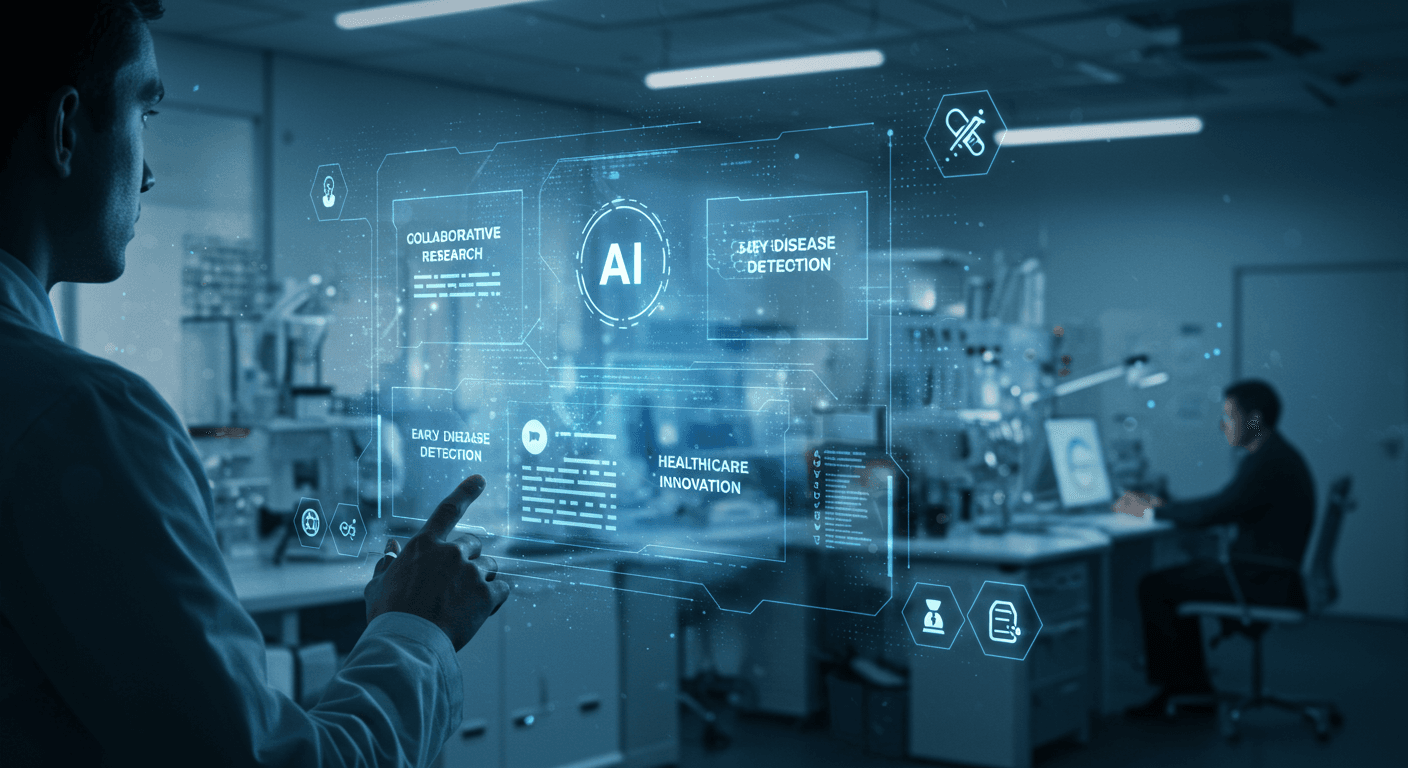
近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの進化は目覚ましく、プレスリリースのタイトル作成においても強力なツールとなりつつあります。AIを活用することで、アイデアの壁打ちや複数パターンの洗い出しが効率的に行え、広報担当者の業務負担を軽減できます。しかし、AIを使いこなすには、その特性を理解し、適切な指示(プロンプト)を与えるスキルが不可欠です。ここでは、AIをタイトル作成に活用するメリット・デメリットから、効果的なプロンプトの書き方までを解説します。
AIタイトル作成ツールのメリット・デメリット
AIをタイトル作成に導入することには、大きなメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。両者を正しく理解し、賢く活用することが重要です。
メリット:
- 時間短縮と効率化:リリースの要点を入力するだけで、瞬時に複数のタイトル案を生成してくれます。アイデア出しの時間を大幅に短縮できるのが最大の利点です。
- 多様な視点の獲得:自分では思いつかないような切り口や表現のタイトル案を提示してくれるため、思考の幅が広がります。マンネリ化を防ぎ、新しい発想を得るきっかけになります。
- 客観的な提案:AIは感情や思い込みに左右されず、入力された情報に基づいて客観的なタイトル案を生成します。独りよがりなタイトルになるのを防ぐ一助となります。
デメリット:
- 情報の正確性の欠如:AIは事実に基づかない情報を生成する(ハルシネーション)可能性があります。「業界初」など、事実確認が必須な表現を誤って使うことがあるため、ファクトチェックは人間が必ず行う必要があります。
- 紋切り型の表現:学習データに依存するため、時としてありきたりで、独自性やインパクトに欠ける表現になることがあります。
- 文脈理解の限界:業界特有のニュアンスや、企業のブランドイメージといった深い文脈を完全に理解することは困難です。最終的な調整は人間の感性が必要です。
効果的なプロンプト(指示文)の書き方とコツ
AIから質の高いタイトル案を引き出すためには、指示文である「プロンプト」の作り込みが鍵となります。漠然とした指示ではなく、具体的で詳細な情報を提供することが、望む成果を得るためのコツです。
効果的なプロンプトに含めるべき要素:
- 役割の指定:「あなたは経験豊富な広報のプロです」「あなたは大手新聞社の記者です」のように、AIに特定の役割を与えることで、その立場に沿った専門的なアウトプットが期待できます。
- プレスリリースの要約:5W1H(誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どのように)を明確に記述し、ニュースの核心を伝えます。
- ターゲットメディア:「経済新聞向け」「IT専門ウェブメディア向け」「女性向けライフスタイル誌向け」など、想定するメディアを具体的に指定します。
- 含めたいキーワード:タイトルに必ず入れたい企業名、サービス名、特定のキーワード(例:「DX」「サステナビリティ」)を明記します。
- トーンの指定:「信頼性が高く、フォーマルなトーンで」「キャッチーで読者の興味を引くトーンで」など、希望する雰囲気を伝えます。
- 制約条件:「30文字以内で」「数字を必ず入れてください」「誇張表現は避けてください」といった、守ってほしいルールを具体的に指示します。
- 出力形式の指定:「10個のタイトル案を提案してください」「サブタイトルもセットで考えてください」のように、欲しいアウトプットの形式を明確にします。
プロンプトの具体例:
# 命令書あなたは、経験豊富なIT業界専門の広報コンサルタントです。以下の情報に基づいて、メディアの記者が思わずクリックしたくなるような、魅力的で分かりやすいプレスリリースのタイトル案を10個、サブタイトルとセットで提案してください。# 制約条件・メインタイトルは30文字前後・サブタイトルは40文字前後・タイトルには必ず「株式会社Next SaaS」と「ConnectFlow」という固有名詞を入れる・ターゲットメディアは、IT専門メディアとビジネス系ウェブメディア・専門用語を避け、導入メリットが伝わるようにする# プレスリリースの要約・誰が:株式会社Next SaaS・何を:ビジネスチャット、Web会議、ファイル共有を統合した新コミュニケーションツール「ConnectFlow」・いつ:2024年8月1日・なぜ:複数のツールを使い分けることによる情報分断や業務の非効率を解決するため・特徴:1つのアプリで全てのコミュニケーションが完結。AIによる自動要約機能で会議の議事録作成が不要に。・価格:月額1,200円/1ユーザーこのように詳細なプロンプトを用意することで、AIはあなたの意図を深く理解し、より精度の高いタイトル案を生成してくれるでしょう。
タイトルだけじゃない!メディア掲載を後押しするプレスリリースの基本構成

魅力的なタイトルで記者の関心を引くことに成功したら、次はその期待に応える分かりやすい本文を用意する必要があります。プレスリリースには、情報を正確かつ効率的に伝えるための基本的な「型」が存在します。この構成に沿って書くことで、記者は必要な情報を素早く見つけ出すことができ、記事化の可能性がさらに高まります。ここでは、メディア掲載を後押しするプレスリリースの王道とも言える基本構成と、各パートの書き方のポイントを解説します。
リード文:タイトルの内容を補足し、本文へ誘導する
リード文は、タイトルの直後に置かれる、プレスリリース全体の要約文です。本文を読み進めてもらうための導入の役割を果たします。記者はタイトルとこのリード文を読んで、記事にする価値があるかを最終判断することが多いため、非常に重要なパートです。
書き方のポイント:
- タイトルの内容をより具体的に、5W1Hを網羅して記述します。
- 文字数は200〜300字程度で簡潔にまとめます。
- 最も伝えたいニュースの核心から書き始め、時系列に沿って説明する必要はありません。
- このリード文だけで、リリースの全体像が把握できるように構成します。
リード文が分かりにくいと、記者はその先を読む意欲を失ってしまいます。タイトルで示したニュースバリューを、ここで改めて明確に伝えましょう。
本文:5W3Hで詳細を分かりやすく伝える
本文では、リード文で示した内容をさらに掘り下げ、詳細な情報を提供します。ここでは、ニュースの基本要素である5W1Hに、「How much(いくらで)」「How many(どのくらい)」「How in the future(今後の展開は)」を加えた「5W3H」を意識すると、情報の網羅性が高まります。
書き方のポイント:
- 背景・目的(Why):なぜこの商品開発や取り組みを行うに至ったのか、社会的な背景や市場の課題を説明します。
- 製品・サービスの詳細(What/How):具体的な仕様、特徴、利用方法などを記述します。必要に応じて箇条書きや小見出しを使い、視覚的に分かりやすく整理しましょう。
- 今後の展望(How in the future):今後の売上目標や事業展開、バージョンアップの予定などを示し、将来性をアピールします。
- 関係者のコメント:代表者や開発担当者のコメントを入れることで、ニュースにストーリー性や人間味を加えることができます。
問い合わせ先:記者がすぐに連絡できる情報を明記
プレスリリースの末尾には、必ず問い合わせ先を明記します。記者が記事化を検討する際、追加情報や取材の申し込みで連絡してくる可能性があるため、スムーズに対応できる体制を整えておくことが重要です。
明記すべき情報:
- 企業名:正式名称を記載します。
- 部署名・担当者名:広報部など、メディア対応が可能な部署と担当者名をフルネームで記載します。
- 電話番号:日中、確実につながる番号を記載します。
- メールアドレス:担当者がすぐに確認できるメールアドレスを記載します。
- 企業サイトURL:企業の公式サイトのURLを記載します。
- 関連資料:製品サイトのURLや、高解像度の写真・ロゴデータをダウンロードできるURLを添付すると親切です。
これらの情報が正確に記載されていることは、企業の信頼性を示す上でも不可欠です。記者がストレスなく連絡できる環境を整えることも、広報の重要な役割の一つです。
作成後に確認!プレスリリース配信のポイントと注意点
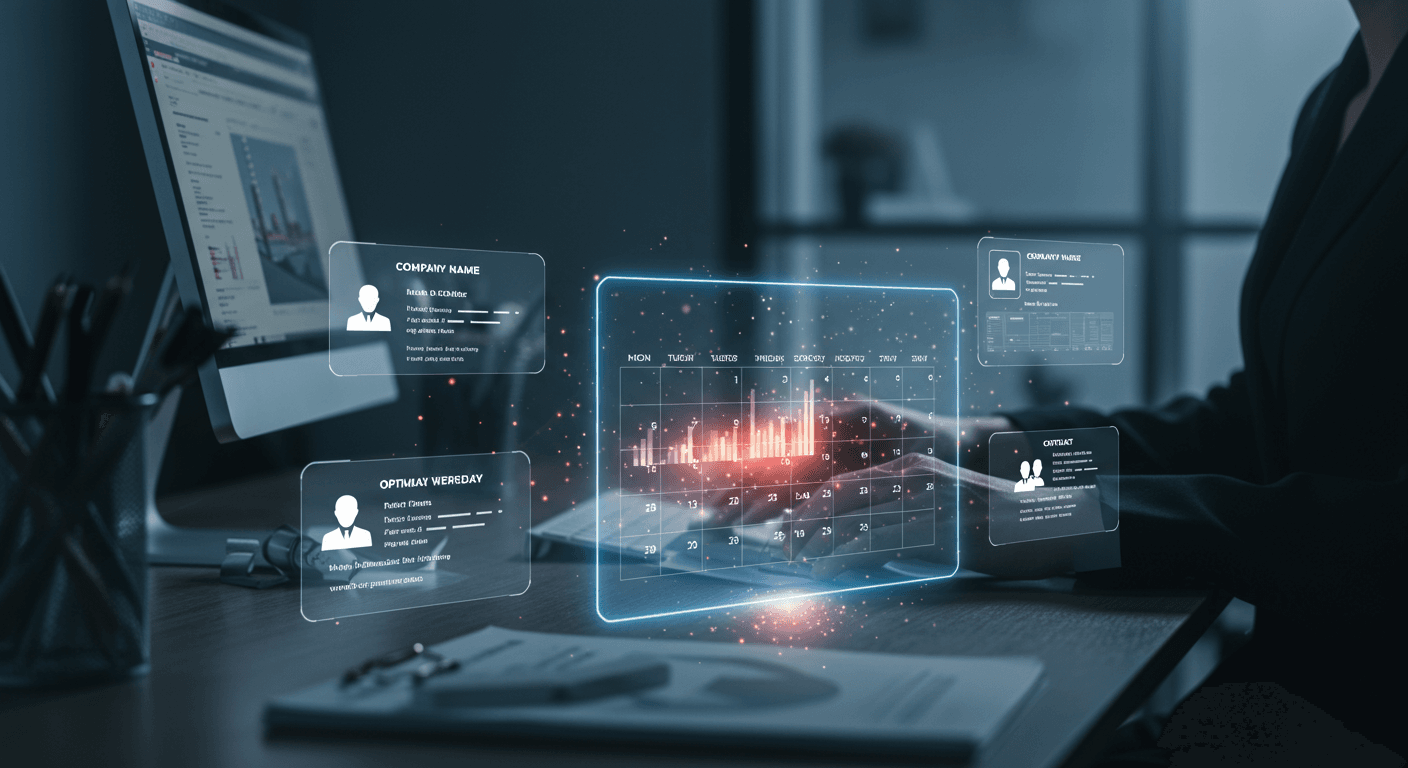
完璧なプレスリリースを作成しても、それが適切な相手に、適切なタイミングで届かなければ意味がありません。配信のプロセスにも、メディア掲載の確率を高めるための重要なポイントが存在します。ここでは、配信タイミングの選び方と、配信前に必ず確認すべき最終チェックリストを紹介します。この最後のひと手間が、あなたの努力を成果に結びつけます。
最適な配信タイミングは?曜日と時間帯の選び方
プレスリリースの配信タイミングは、メディア関係者の働き方に合わせて戦略的に選ぶ必要があります。一般的に、記者が情報をチェックし、記事を執筆しやすい時間帯を狙うのが効果的です。
曜日:週明けの月曜日は会議が多く、週末の金曜日は週の締め切りに追われているため、比較的落ち着いて情報を確認できる火曜日から木曜日が最適とされています。
時間帯:始業直後や昼休み直後は避け、記者がデスクで業務に集中している可能性が高い午前10時〜11時頃、または午後1時〜3時頃が狙い目です。
ただし、これはあくまで一般論です。業界やメディアの特性によって最適なタイミングは異なります。例えば、夕方のニュース番組を狙うなら午前中に、Webメディアの速報を狙うなら発表と同時に、といった調整が必要です。
| 曜日 | 時間帯 | 推奨度 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 午前・午後 | △ | 週明けの会議やメール処理で多忙なため、見逃されやすい。 |
| 火〜木曜日 | 10:00-11:00 / 13:00-15:00 | ◎ | 記者が比較的落ち着いており、情報収集や記事執筆に時間を割きやすい。 |
| 金曜日 | 午前 | ○ | 週末ネタを探しているメディアには有効だが、午後は締め切りで多忙。 |
| 土日・祝日 | 終日 | × | 基本的に休みの記者が多く、緊急性の高いニュース以外は読まれない。 |
配信前の最終チェックリスト【11項目】
配信ボタンを押す前に、一度立ち止まって最終確認を行いましょう。小さなミスが、企業の信頼を損なうこともあります。以下のチェックリストを使って、隅々まで見直してください。
- タイトルは魅力的で分かりやすいか?(30文字前後、結論ファースト、数字や固有名詞は入っているか)
- 誤字脱字はないか?(複数人でダブルチェック推奨)
- 日付や曜日に間違いはないか?(特に発表日、発売日、イベント開催日)
- 固有名詞(企業名、サービス名、人名)は正確か?
- 数字やデータに間違いはないか?(売上、調査結果など)
- リード文だけで全体像が伝わるか?
- 専門用語や分かりにくい表現を使っていないか?
- 誇張表現や根拠のない断定的な表現はないか?(薬機法、景表法は大丈夫か)
- 問い合わせ先の情報は正確か?(電話番号、メールアドレスなど)
- 画像や参考資料のリンクは正しく機能するか?
- 配信先のメディアリストは適切か?(内容と関連性のないメディアに送っていないか)
これらの項目をすべてクリアして初めて、自信を持ってプレスリリースを世に送り出すことができます。
プレスリリースのタイトル作成に関するよくある質問(FAQ)
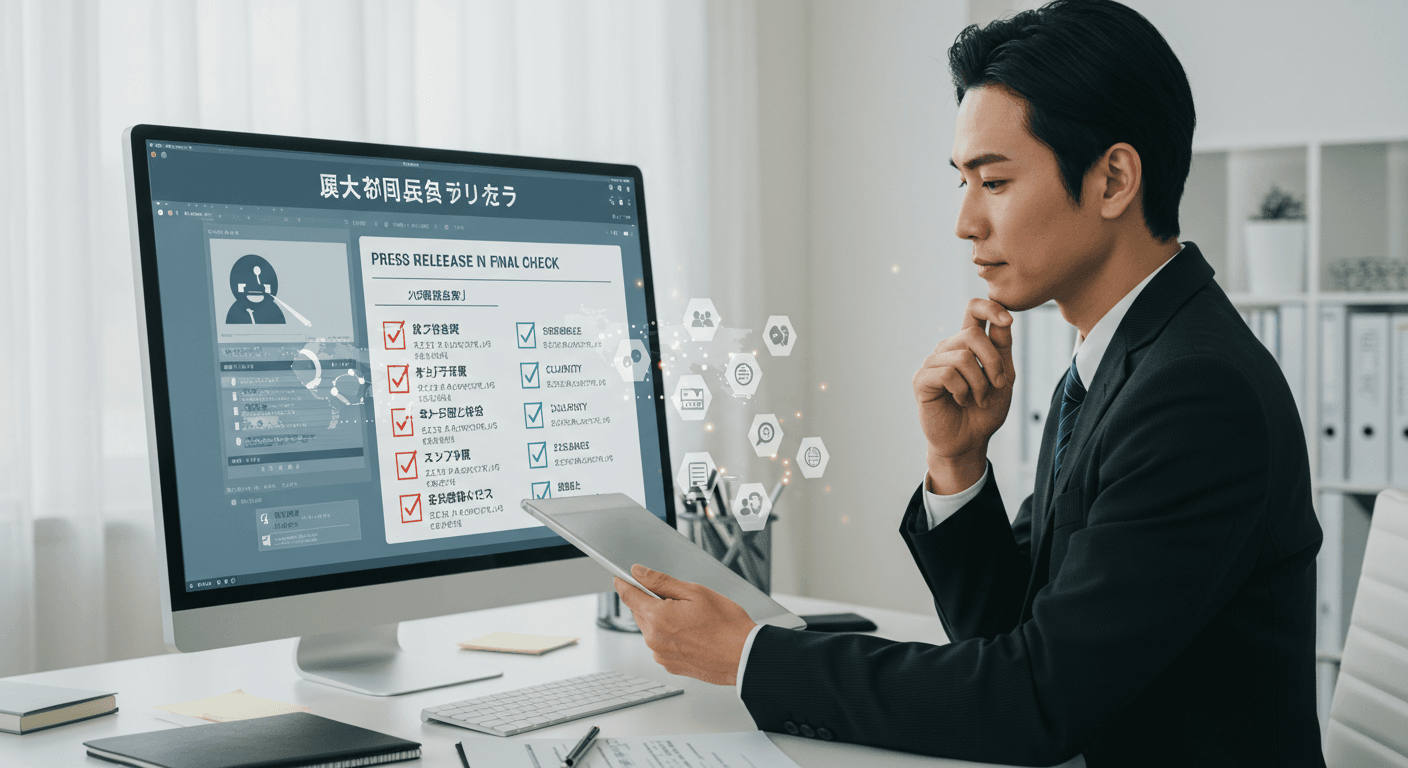
ここでは、プレスリリースのタイトル作成に関して、広報担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。疑問点を解消し、より効果的なタイトル作成に役立ててください。
Q. キャッチーな表現を使っても良いですか?
Q. キャッチーな表現を使っても良いですか?
A. 注意が必要です。記者の興味を引くことは重要ですが、プレスリリースは企業の公式発表という側面も持ちます。あまりに砕けすぎた表現や、流行り言葉の多用は、企業の信頼性を損なう可能性があります。特に、BtoBや金融、医療といった信頼性が重視される業界では、誠実でフォーマルなトーンが好まれます。キャッチーさを狙う場合でも、「!」や「?」の多用は避け、客観的な事実に基づいた表現の範囲内に留めるのが賢明です。大切なのは、奇をてらうことではなく、ニュースの価値を正確に伝えることです。
Q. タイトルが思いつかない時はどうすればいいですか?
Q. タイトルが思いつかない時はどうすればいいですか?
A. いくつか対処法があります。まず、本記事で紹介した「9つの基本原則」や「目的別例文」に立ち返り、切り口を変えてみましょう。次に、競合他社のプレスリリースを参考に、どのようなタイトルがメディアに取り上げられているかを分析するのも有効です。また、ChatGPTなどのAIツールにリリースの要点を入力し、アイデアの壁打ち相手として活用するのも良い方法です。最終的には、一人で抱え込まず、社内の別部署の人など、第三者に相談して客観的な意見をもらうことをお勧めします。
Q. メディアの種類によってタイトルは変えるべきですか?
Q. メディアの種類によってタイトルは変えるべきですか?
A. 理想を言えば「変えるべき」です。時間とリソースに余裕があれば、メディアの特性に合わせてタイトルをカスタマイズするのが最も効果的です。例えば、経済新聞向けには「市場へのインパクト」や「経済効果」を強調し、IT専門メディア向けには「技術的な新規性」を、ライフスタイル誌向けには「読者の生活がどう豊かになるか」をアピールするなど、切り口を変えます。ただし、全メディアに個別対応するのは困難な場合も多いでしょう。その場合は、最もターゲットとしたいメディア層に響くタイトルを一つ作り込み、それを基本として配信するのが現実的な対応です。
まとめ:ニュース価値を伝えるタイトルでメディア掲載を勝ち取ろう
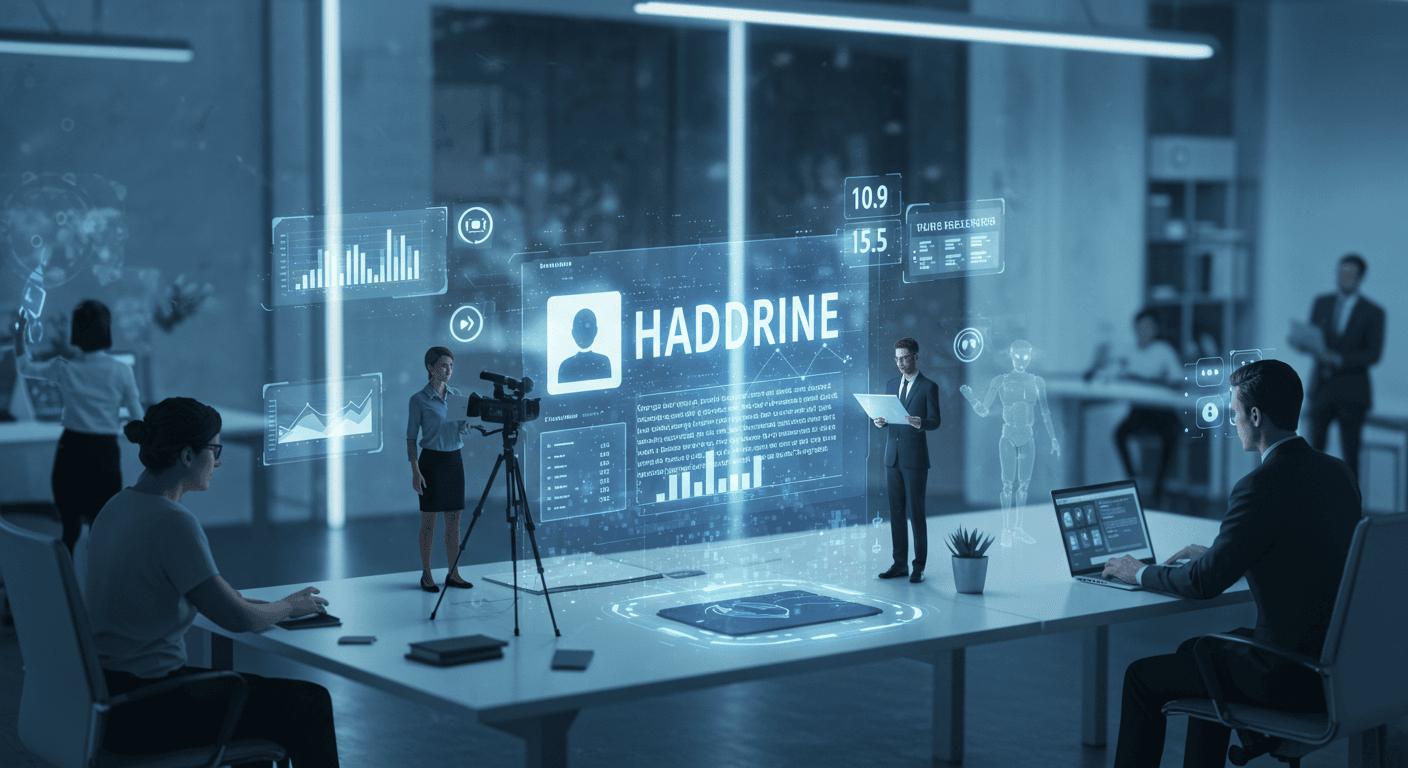
本記事では、メディアに取り上げられるプレスリリースのタイトル作成術について、基本原則から具体的な例文、業界別のポイント、さらにはAIの活用法まで網羅的に解説しました。多忙な記者の目に留まるためには、タイトルのわずか30文字前後で、ニュースの価値を的確かつ魅力的に伝える必要があります。
結論ファースト、具体的な数字、客観的な表現といった基本を徹底し、自社の発表が持つ「ニュースバリュー」は何かを深く掘り下げることが成功の鍵です。今回紹介したテクニックとチェックリストを活用し、戦略的にタイトルを作成することで、メディア掲載の可能性は飛躍的に高まります。ぜひ、次のプレスリリースから実践してみてください。