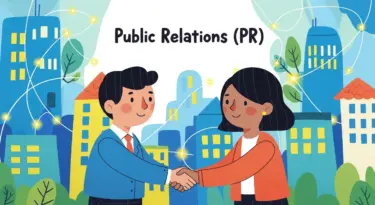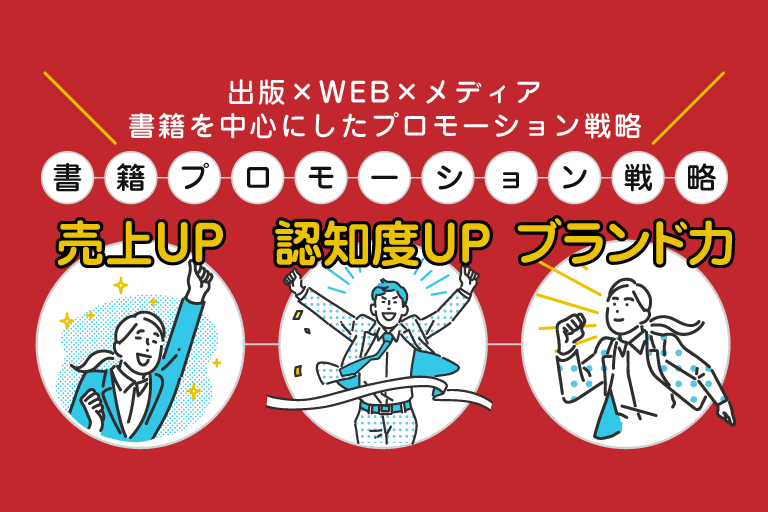- 1 Table of Contents
- 1.1 そもそもマーケティングファネルとは?広報との関係性を理解する
- 1.2 マーケティングファネルの主要な3種類と広報の役割
- 1.3 【実践編】広報施策を最大化するファネル段階別アクションプラン
- 1.4 【応用編】採用広報におけるマーケティングファネル活用戦略
- 1.5 「マーケティングファネルは古い」は本当か?現代における有効性
- 1.6 まとめ:マーケティングファネルと広報を連携させ、成果を最大化しよう
- 1.7 マーケティングファネルと広報に関するよくある質問(FAQ)
Table of Contents
- そもそもマーケティングファネルとは?広報との関係性を理解する
- マーケティングファネルの基本モデル「パーチェスファネル」
- 広報(PR)がファネル全体に与える影響とは?
- なぜ今、マーケティングと広報の連携が不可欠なのか
- マーケティングファネルの主要な3種類と広報の役割
- 1. 購買行動モデル「パーチェスファネル」
- 2. 購買後の行動を重視する「インフルエンスファネル」
- 3. 2つを統合した「ダブルファネル」
- 【実践編】広報施策を最大化するファネル段階別アクションプラン
- TOFU(認知段階):ブランドの「存在」を広く知らせる広報戦略
- 施策例:プレスリリース、メディアリレーションズ、イベント開催
- KPI設定例:指名検索数、メディア掲載数、サイトUU数
- MOFU(興味・関心/比較・検討段階):専門性と信頼を「醸成」する広報戦略
- 施策例:オウンドメディアでの事例記事、専門家インタビュー、調査レポート発表
- KPI設定例:記事の読了率、ホワイトペーパーDL数、問い合わせ件数
- BOFU(行動段階):最後のひと押しを「後押し」する広報戦略
- 施策例:顧客の成功事例、第三者機関からの受賞・評価、経営者のメッセージ発信
- KPI設定例:コンバージョン率(CVR)、商談化率、導入事例からの問い合わせ数
- 比較表:ファネル段階別の広報施策とKPI
- 【応用編】採用広報におけるマーケティングファネル活用戦略
- 採用ファネルの各段階と候補者の心理
- 採用ブランディングを強化する施策事例
- ボトルネックの特定方法と改善アプローチ
- 「マーケティングファネルは古い」は本当か?現代における有効性
- なぜ「古い」と言われるのか?その背景
- BtoBや採用広報で今なお有効な理由
- フライホイールモデルとの違いと連携の考え方
- まとめ:マーケティングファネルと広報を連携させ、成果を最大化しよう
- マーケティングファネルと広報に関するよくある質問(FAQ)
「マーケティングと広報の連携がうまくいかず、施策の効果を最大化できていない」「採用広報に力を入れたいが、具体的に何から手をつければいいか分からない」——。そんな悩みを抱えていませんか?多くの企業でマーケティングと広報は別々の部署として動いており、その連携不足が大きな機会損失を生んでいます。特に、採用市場が激化する現代において、候補者の心をつかむためには、両者を連携させた戦略的なアプローチが不可欠です。この記事では、顧客や候補者の行動プロセスを可視化する「マーケティングファネル」を軸に、広報活動を連携させるための具体的なアクションプランを徹底解説します。ファネル各段階でのKPI設定やボトルネックの特定方法、そして採用広報への応用まで、明日から実践できる知識を提供します。
そもそもマーケティングファネルとは?広報との関係性を理解する
マーケティングファネルの最も基本的なモデルが「パーチェスファネル」です。これは、顧客の購買行動を「認知」「興味・関心」「比較・検討」「購入」というステップに分類します。最初の「認知」段階では、まだ自社を知らない潜在顧客がターゲットです。次に「興味・関心」を持ってもらい、「比較・検討」を経て、最終的に「購入」へと導きます。各段階でターゲットとなる層の母数や心理状態が異なるため、それぞれに適したマーケティング施策や広報活動が求められます。
広報(PR)がファネル全体に与える影響とは?
広報(PR)は、単に「認知」段階でメディア露出を増やすだけの活動ではありません。第三者であるメディアや専門家からの客観的な情報は、ファネルの全段階において顧客の意思決定に強力な影響を与えます。例えば、興味・関心段階では専門誌でのレビュー記事が信頼性を高め、比較・検討段階では顧客の成功事例が導入の決め手となることがあります。このように、広報は広告とは異なる「信頼性の醸成」という役割を担い、ファネル全体の通過率を高める重要な鍵となります。
マーケティングファネルの基本モデル「パーチェスファネル」

マーケティングファネルには、顧客の行動モデルの変化に合わせていくつかの種類が存在します。ここでは主要な3つのファネルを紹介し、それぞれにおける広報の役割を解説します。自社のビジネスモデルや目的に合わせて、どのファネルを意識すべきかを考えましょう。
1. 購買行動モデル「パーチェスファネル」
前述の通り、最も古典的で基本的なモデルです。顧客が商品を「認知」し、「興味・関心」を持ち、「比較・検討」を経て「購入」に至るまでの一方向のプロセスを描きます。広報の役割は、各段階で顧客の心理的なハードルを下げ、次のステップへスムーズに移行させることです。例えば、認知段階では話題性を喚起し、検討段階では信頼できる情報を提供して購買意欲を後押しします。
2. 購買後の行動を重視する「インフルエンスファネル」
インフルエンスファネルは、顧客が商品を購入した後の行動に着目したモデルです。購入した顧客がその商品を「継続」利用し、さらにSNSなどで「紹介・共有」することで、新たな顧客の「発信」源となるプロセスを示します。広報活動としては、顧客満足度を高めるための情報提供や、優良顧客の成功事例を発信することで、ポジティブな口コミ(UGC)が生まれやすい環境を整える役割を担います。
3. 2つを統合した「ダブルファネル」
ダブルファネルは、購買前の「パーチェスファネル」と購買後の「インフルエンスファネル」を統合したモデルです。新規顧客獲得から既存顧客のファン化、そしてそのファンによる新規顧客の創出まで、一連のサイクルとして捉えます。広報は、このサイクル全体を円滑に回すための潤滑油のような存在です。一貫したブランドメッセージを発信し続けることで、顧客との長期的な関係性を構築します。
なぜ今、マーケティングと広報の連携が不可欠なのか
TOFU(Top of the Funnel)は、ファネルの最上層部です。この段階の目的は、まだ自社の製品やサービス、さらには解決すべき課題自体に気づいていない潜在顧客層に対して、まずは「存在を知ってもらう」ことです。ここでは、できるだけ多くの人々にリーチすることが重要になります。
【実践編】広報施策を最大化するファネル段階別アクションプラン
指名検索数:自社名や製品・サービス名での検索回数。メディア露出後に増加しているかを確認します。
メディア掲載数(アーンドメディア):広告費をかけずに獲得したWebメディアや新聞、雑誌などでの掲載件数やその質(掲載先の権威性など)。
WebサイトのUU数(ユニークユーザー数):施策実施後に、自社サイトを訪れたユーザーがどれだけ増えたかを測定します。
MOFU(興味・関心/比較・検討段階):専門性と信頼を「醸成」する広報戦略
MOFU(Middle of the Funnel)は、ファネルの中間層です。自社の存在を認知し、ある程度の興味を持った見込み顧客がターゲットです。この段階の目的は、より深い情報を提供することで、彼らの課題解決に役立つ存在として「専門性と信頼を醸成」し、比較検討の土俵に乗ることです。
施策例:プレスリリース、メディアリレーションズ、イベント開催
記事の読了率・滞在時間:オウンドメディアの記事が最後までしっかり読まれているか。コンテンツの質を測る指標です。
ホワイトペーパーや資料のダウンロード(DL)数:見込み顧客がより詳細な情報を求めている証拠であり、質の高いリード獲得数の指標となります。
Webサイトからの問い合わせ件数:製品やサービスに関する具体的な質問や相談の数。購買意欲の高まりを示します。
BOFU(行動段階):最後のひと押しを「後押し」する広報戦略
BOFU(Bottom of the Funnel)は、ファネルの最下層です。複数の選択肢の中から最終決定を下そうとしている、購買意欲が非常に高い見込み顧客がターゲットとなります。この段階の目的は、安心感や共感を醸成し、競合ではなく自社を選んでもらうための「最後のひと押し」をすることです。
施策例:オウンドメディアでの事例記事、専門家インタビュー、調査レポート発表
コンバージョン率(CVR):問い合わせや資料請求から、実際の購入や契約に至った割合。施策が最終成果にどれだけ貢献したかを測ります。
商談化率:獲得したリード(見込み顧客)のうち、具体的な商談に進んだ割合。リードの質を評価する指標です。
導入事例ページ経由の問い合わせ数:特定の導入事例を読んだユーザーからの問い合わせ数。コンテンツが最後のひと押しとして機能したかを測ります。
比較表:ファネル段階別の広報施策とKPI
これまでの内容を一覧で確認できるよう、以下の表にまとめました。自社の広報活動がどの段階に貢献しているか、そして次に打つべき施策は何かを考える際の参考にしてください。
ファネル段階 | 目的 | 広報施策例 | 主要KPI例 |
|---|---|---|---|
TOFU | 広く存在を知ってもらう | ・プレスリリース配信 | ・指名検索数 |
MOFU | 専門性と信頼を醸成する | ・オウンドメディアでの事例記事 | ・記事の読了率 |
BOFU | 最後のひと押しで選ばれる | ・顧客の成功事例(ROI明記) | ・コンバージョン率(CVR) |
施策例:顧客の成功事例、第三者機関からの受賞・評価、経営者のメッセージ発信
採用ファネルは一般的に「認知」「興味・関心」「応募」「選考」「内定・入社」の段階で構成されます。各段階で候補者の心理状態は大きく異なります。
認知:「こんな会社があるんだ」と知る段階。
興味・関心:「どんな事業をしているんだろう?」「どんな人が働いているんだろう?」と関心を持つ段階。
応募:「この会社で働いてみたい」と具体的なアクションを起こす段階。
選考・入社:「本当にこの会社でいいのか」と最終判断を下す段階。これらの心理に合わせた情報提供が不可欠です。
【応用編】採用広報におけるマーケティングファネル活用戦略
採用ファネルを分析する最大のメリットは、プロセスの「ボトルネック(滞留点)」を特定できることです。例えば、「採用サイトへのアクセスは多いのに、応募数が少ない」のであれば、MOFUからBOFUへの移行がボトルネックです。この場合、エントリーフォームが複雑すぎる、募集要項の魅力が伝わっていない、などの原因が考えられます。改善アプローチとしては、募集職種の社員インタビュー記事への導線を強化したり、エントリーフォームを簡略化したりするなどの対策が有効です。
採用ファネルの各段階と候補者の心理
「古い」と言われる主な理由は、現代の顧客の購買行動が、ファネルのように上から下へ一直線に進むとは限らないからです。SNSでいきなり商品を知って購入したり(BOFUから始まる)、一度ファネルから離脱した顧客が別の情報に触れて戻ってきたりと、その道のりは非常に複雑化・多様化しています。この非線形な動きを、従来の直線的なファネルモデルでは捉えきれないという指摘です。
BtoBや採用広報で今なお有効な理由
しかし、特にBtoB領域や採用広報においては、ファネルの考え方は依然として非常に有効です。なぜなら、高額な製品の導入や就職・転職といった意思決定は、個人の衝動的な買い物とは異なり、比較的慎重かつ論理的な情報収集と検討のプロセスを経るからです。この構造的なプロセスを可視化し、各段階の課題を特定・改善するための分析フレームワークとして、ファネルは今なお強力なツールであり続けます。
採用ブランディングを強化する施策事例
本記事では、マーケティングファネルの基本から、広報活動を連携させるための具体的なアクションプラン、そして採用広報への応用までを解説しました。マーケティングと広報は、もはや別々に語れるものではありません。ファネルという共通のフレームワークを持つことで、両者の施策は有機的に結びつき、一貫したブランド体験を顧客や候補者に提供できます。まずは自社のファネルの現状を分析し、どこにボトルネックがあるのかを特定することから始めてみましょう。そして、各段階に最適な広報施策を戦略的に実行することで、事業全体の成果を最大化していきましょう。
マーケティングファネルと広報に関するよくある質問(FAQ)
Q1. マーケティングと広報の連携を始めるにあたり、最初のステップは何ですか?
A1. 最初のステップは、両部門で共通の目標とKPIを設定することです。例えば、「今期はMOFU(検討段階)のリードを20%増やす」といった具体的な目標を立て、その達成のためにマーケティング部門はWeb広告を、広報部門はオウンドメディアでの事例記事制作を、といった形で役割分担と連携の計画を立てることから始めましょう。
Q2. 広報活動の効果測定は難しいと言われますが、ファネルを使えば可能ですか?
A2. はい、ファネルのフレームワークを用いることで、広報活動の貢献度を可視化しやすくなります。例えば、特定のメディア掲載後に指名検索数やサイトへの流入がどれだけ増えたか(TOFUへの貢献)、導入事例記事を公開した後にホワイトペーパーのダウンロード数がどれだけ伸びたか(MOFUへの貢献)などを測定することで、活動の成果を定量的に評価することが可能です。
Q3. 中小企業でリソースが限られている場合、どのファネル段階の広報に注力すべきですか?
A3. リソースが限られている場合、まずはBOFU(行動段階)に近い領域から着手するのが効率的です。具体的には、既存顧客の成功事例を作成し、Webサイトや商談の場で活用することです。これは、最も購買意欲の高い層に直接アプローチでき、信頼性を高める効果が絶大だからです。成功事例が蓄積してきたら、それを基にMOFU、TOFUへと施策を広げていくのが良いでしょう。